こんにちは、中小企業診断士(登録予定)のヨシローです。
今回は中小企業診断士合格までにどのようなスケジュールで勉強してきたのか紹介します!
- 勉強期間は合計1,000時間程度、約1年でストレート合格
- 勉強方法は1次試験が通信(診断士ゼミナール)、2次試験が独学
この記事でわかること
・中小企業診断士試験ストレート合格に必要な学習スケジュールがわかる!
・1次試験、2次試験の各科目の進め方がわかる!
・現在の勉強状況と比較することで、進捗状況が把握できる!

ぜひ学習スケジュールを参考にしてください!
全体スケジュール
中小企業診断士に関係する勉強は、以下のように進めていきました。私の場合、中小企業診断士の試験勉強の前に、前哨戦として、簿記2,3級の勉強をしましたので、合わせてそのスケジュールも書きました。
- 2021年8月:簿記3級の学習開始→合格
- 2021年9月:簿記2級の勉強開始
- 2021年11月:簿記2級合格
- 2022年1月:診断士ゼミナールで勉強開始
- 2022年4月:企業経営理論、経済学・経済政策、財務会計、運営管理の講義を1周視聴終了
- 2022年5月:プライベートが忙しくなり、勉強中断
- 2023年2月:勉強再開(講義視聴から全てやり直し)
- 2023年8月:1次試験受験
- 2023年9月:1次試験合格
- 2023年9月:2次試験勉強開始
- 2024年1月:2次筆記試験合格
- 2024年1月:口述試験対策開始→口述試験合格
中小企業診断士の受験を検討し始めてから、2年半ぐらいでなんとか合格できました。次からは、各期間の詳細をそれぞれ書いていきます。
中小企業診断士の勉強開始前
診断士試験の勉強開始前に、関係のある資格として簿記3級・2級に取り組みました。理由は、中小企業診断士の受験について調べていると、診断士試験の要は“財務・会計“であり、簿記2級相当が必要という内容を見たからです。
会社の実務では全く関係がないので、もし、簿記2級まで学習して、自分にはあわないようだったら中小企業診断士は諦めようと思い、学習をスタートしました。
簿記3級、簿記2級ともに、テキストと問題集(TAC出版の”みんなが欲しかったシリーズ”)を一冊、たまにふくしままさゆきさんのYoutube見ながら勉強しました。
最終的に簿記2級の習熟度としては7~8割程度で、少し理解しきれない部分もありましたが、中小企業診断士受験にとっては十分な理解度でした。
特に、1次試験の財務・会計では半分程度は簿記2級と被るため、完全に勉強不要でした。残りの部分も簿記2級が取れるレベルであれば、すんなりと理解できると思います。



改めて振り返って見ると、簿記2級を勉強してよかったなと思います!
1次試験
2023年2月から本腰を入れて勉強を開始しました。
勉強は理論科目→暗記科目の順番で行いました。具体的には、企業経営理論→経済学→運営管理→財務会計→経営情報システム→経営法務→中小企業経営です。各科目ともに以下の4ステップで勉強していきました。
- 診断士ゼミナールの講義とテキスト
- 診断士ゼミナールの問題集
- TAC出版のスピード問題集
- 過去問(5年分程度)
勉強のペース感としては、GW前までに理論科目(企業経営理論〜財務会計)診断士ゼミナールの講義とテキスト・問題集まで完了していました。
GW以降は暗記科目の勉強開始と理論科目の過去問を解いていました。TACの1次公開模試(7月上旬)までに、中小企業経営・中小企業政策以外はスピード問題集・過去問を一通り解き終わり、苦手な問題の復習を残すのみでした。
中小企業経営・中小企業政策は全然手をつけられておらず、残り1ヶ月で診断士ゼミナールの講義・テキストと問題集までは完了しました。(ただ、スピード問題集は勉強終了できませんでした・・)
最終的な点数は以下の通りです。受験した感想としては、LEC 1次ステップアップ模試は比較的に基礎的な問題が多かったような印象です。その後に解いた過去問やTAC 1次公開模試は、時折難しい問題があり高得点は難しい印象を受けました。。
本番の試験では、準備の間に合わなかった中小企業経営・中小企業政策以外は無事に科目合格点を超えることができました!
| テスト | 経済学・ 経済政策 | 財務・会計 | 企業経営理論 | 運営管理 | 経営法務 | 経営情報システム | 中小企業経営・ 中小企業政策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC 1次ステップアップ模試 | 44 | 72 | 69 | 59 | 56 | 64 | 56 | 420 |
| TAC 1次公開模試 | 72 | 64 | 56 | 61 | 44 | 68 | 38 | 403 |
| 本番 | 72 | 72 | 72 | 70 | 84 | 76 | 56 | 502 |



模試で悪い科目があっても大丈夫です!
まだ時間はあるので十分間に合います!
2次筆記試験
2次試験の勉強は、1次試験が終了してから着手しました。(本当はGWあたりに2次試験の勉強をしようと思っていましたが、上述の通り余裕がなく全く手をつけられませんでした。。。)
1次試験終了後に自己採点をすぐに行い、合格を確認してから慌てて2次試験の勉強方法を調べました。
2次試験は1次試験と異なり記述式の試験で、正当が公表されない試験のため、答えのない中で勉強しなければならないことが分かりました。
また、1次試験と大きく試験内容が異なることから、いくつかの通信講座(診断士ゼミナールやスタディング)の講座では、2次試験対策としては不十分であることも調べていく中で分かりました。
独学か予備校(TACやEBAなど)で大変悩みましたが、1次試験に一度合格すると、翌年の1次試験をスキップできることを踏まえ、今年は独学でチャレンジすることとしました。
使用したテキストは、事例Ⅰ〜Ⅲはふぞろいシリーズ、事例Ⅳではふぞろいシリーズに加え、30日完成と全知全ノウを用いました。
勉強の進め方は、以下のようなステップで勉強を進めていきました。
事例Ⅳ:30日完成を2~3周
事例Ⅰ〜Ⅲ:過去問(平成28~30年)+ふぞろいシリーズ
事例Ⅳ:全知全ノウのA・B問題を2周
事例Ⅰ〜Ⅲ:過去問(令和元年~4年)+ふぞろいシリーズ
事例Ⅳ:過去問(令和元年〜4年)+ふぞろいシリーズ
自己採点、EBAでの再現答案の採点サービス、本番点数は下表の通りです。
概ね自己採点(自分の肌感)と同じような印象でしたが、事例Ⅳは60点を超えるほど埋めていないため、何らかの補正があったのかなと思っています。
| 採点者 | 事例I | 事例Ⅱ | 事例Ⅲ | 事例Ⅳ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己採点 | A~B | A | C~D | B | A~B |
| EBA | B | A | C | A | B |
| 最終結果 | 63 | 64 | 54 | 65 | 246 |



1次試験後からでも2次筆記試験を合格できますので、
1次試験前に手をつけられていなくても大丈夫です!
2次口述試験
上述の通り、予備校での再現答案の採点サービスでは点数があまり良くなかったので、あまり期待していませんでしたが、まさかの合格でした。そのため、口述試験対策は2次試験の発表後に慌てて取り組みました。
口述試験では、2次筆記試験の事例Ⅰ〜Ⅳから二つの事例について各2問程度質問され、2分程度で口頭で回答する試験となります。
例年、口述試験の合格率は99%程度で基本的には全員合格するような試験です。不合格になった方は、当日時間に間に合わなかった人、あえて受験しなかった人(養成課程に進む為)、面接中に一度も喋らなかった人などと言われています。
でもいざ試験を受ける立場になると、落ちる1%に入ったらどうしようと大変心配になりました。
私は対策として、事例Ⅰ〜Ⅳの復習と支援団体での模擬面接を行いました。
事例の復習は予備校やYoutubeなどの解説を聞き直し、再度各事例を読み込みました。また回答で誤っていた部分も修正し、再度回答を考え直しました。
支援団体での模擬面接は、複数の団体で行なっていましたので、タキプロと一発道場で2回受けました。
総勉強時間は10時間程度だと思いますが、当日は問題なく受け答えでき、無事に口述試験も合格できました。



模擬面接のおかげで当日は落ち着いて受け答えできました。
支援団体の方々、大変ありがとうございました!
まとめ
中小企業診断士試験をストレート合格したヨシローの勉強スケジュールについて紹介しました。
勉強期間としては、簿記の学習を含め概ね1年ほど勉強することでストレート合格できました。
いま受験生の方々は、各科目の進捗や予備校の模試の点数などを比較していただき、今後のスケジュール調整に活用いただければと思います。
これから受験される方は、中小企業診断士試験の受験を受けるかどうかの判断に役立てられれば幸いです。



今後、より詳細な勉強法についても紹介していきたいと思いますので、
乞うご期待ください!

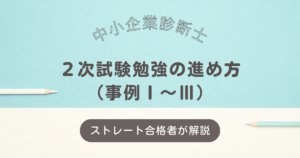
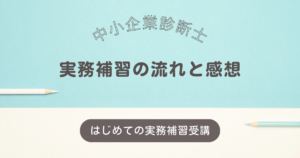
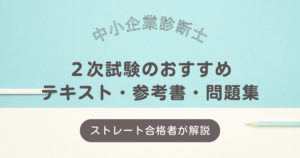
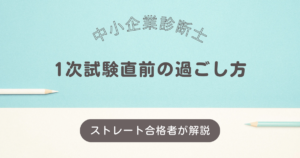


コメント